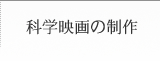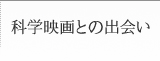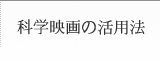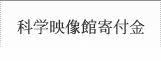- ホーム
- 科学映画の制作
- 生命科学映画と60年

生命科学映画と60年
久米川 今日はお話の機会をいただきありがとうございます。大沼さんは東大の経済学部をご卒業。その大沼さんが映画、しかもドキュメンタリー映画の世界に飛び込まれた。このあたりからお伺いしたいと思います。
大沼 東大在学中、当時は学内で映画サークル活動が盛んでした。私は授業にはあまり関心がなく、映画サークルで一生懸命部活をやっていました。ちょうどそのころ、関川秀雄監督が「きけ わだつみの声」の映画化を進めており、お手伝をする機会がありました。そこで卒業したらぜひ、映画の道にと。自然、生物などに密着した仕事。すなわち、映像を介して自分が住んでいる世界を考えていきたいと思ったんです。従って対象が、肉眼サイズのものか、顕微鏡サイズものか、また望遠鏡的なものかという違いは問題ではない。とにかく対象を映像化し、その世界を把握したいと思ったんです。
久米川 そうすると生命科学映画に舵をきったのもごく自然の流れでしたね。
大沼 私はそう思います。特に細胞の世界は実に面白いですね。たとえば17世紀にレーウェンフークが顕微鏡を発明したことによって微生物が発見され、ひいてはそれが現代の遺伝子までつながる。その少し前にはガリレオがレンズを天体に向けたことがきっかけで望遠鏡がつくられ、それが後に地動説から天動説へと大転換をおこすきっかけになった。顕微鏡と望遠鏡は向きが違うだけで、ある意味そっくり同じものですが、レンズを通して何かを見ることによって、従来人間が持っていた概念が一変する。私たちの世界の把握の仕方に大影響を及ぼすことがあるんだと。これは素晴らしいことですね。顕微鏡でつかめる世界には、人間が人間のことを考える上で、すごく重要な示唆が含まれているはずだなと思うんですよ。

久米川 生命科学映画に関心をお持ちになったことは、よく分かりました。しかし、戦後は劇映画の最盛期でしたね。そういう中で生命科学を対象にしたヨネ・プロダクションの仕事はなかなか厳しいものがあったでしょうね。
大沼 大変でしたね。もちろん小林一人ではありません。岡田桑三さんを中心とした東京シネマとか岩波映画とか、ドキュメンタリー映画をつくる会社がいくつかありましたし、何人もの方がその道で努力され、今でもいい仕事をしている方がおられます。常識を破った仕事に、先輩たちはみんな大変な努力をされたと思います。小林米作はらい菌を撮影したことで有名ですが、らい菌なんて見えるはずがないと皆に笑われた時代に、何か見えるはずだと言ってらい菌を培養し、しかもフィルム寒天にガラスで挟んで、それを顕微鏡下で見るという画期的なことをやったのです。ふつうは染色して閉じ込めて、乾いた、死んだ像を見ていた。動くものを見ることはできなかったんですね。寒天培養の寒天を非常に薄くして、顕微鏡で見えるような仕掛けなんて誰も考えなかった。トライしなかった。しかし、常に自然の神秘、謎に迫ろうとの小林さんのチャレンジ精神は素晴らしかったと思います。
久米川 そうです。小林さんの自然の謎に迫るチャレンジ精神は、本当に素晴らしい。まさに科学映画の父ですね。その代表的な映画が「生命誕生」でしょう。1個の卵から鶏に発育・成長する様子を映像化。この映画は我々に多くの情報をもたらしました、いや今でももたらしています。大変奥の深い映画ですね。この映画がほぼ50年前に制作されたとは驚きです。
大沼 本当のストーリーは制作者が書くのではなく、対象物自身が持っているんですね。
久米川 本当にそうですね。小林さんの仕事は脚本がないんです。今度の映画は、先生"濡れ"ですねの一言。これは骨の中に埋もれ、大切な働きをしている骨細胞の映画製作時の最初の言葉です。撮影時、脚本を見たことはありませんでした。
大沼 そうですね。彼はそういう意味でドキュメンタリストだと思うんです。対象が細胞であるか、動物であるか、人間であるかということですね。彼は科学映画を始める前は、南の島の奥地で原住民と一緒に暮らして、そのドキュメンタリーを撮ったりしていますし、戦時中は従軍カメラマンだったんですね。

顕微鏡に試料を置く
久米川 本当に大変な科学映画制作者。しかし、この小林さんと仕事をされるのはご苦労も多かったと思いますが、大沼さんと小林さんとの接点、そしてどうして2人が一緒に仕事をされるようになったんでしょう。
大沼 私が映画に入ったころ、奇妙なカメラマンがいるなという印象で先輩を見ていたのですが、向うも何かしら私に目をつけたらしくて、呼ばれて、こういうアイデアがあるから、シナリオを書けとか言われたりして、それで親子ほど年が違うんですけど、ヨネさんと呼ぶような間柄になりましてね。ヨネ・プロが始まる前から顕微鏡映画を一緒に撮ったりしていて、当時は日本が戦後の焼け跡的状況の中ですべて人力に頼っていた時代で、たとえば微速度撮影なんかも人手でやっていたんです。助手がストップウオッチをもって、その合図によって10秒ごとにシャッターを切るとか(※)。感度のいいフォトメーターもまだなくて、小林の眼力で1コマに何秒露出すればいいとか決めるんです。ちょっと間違えると、現像しても真っ黒で何も出てこないなんてこともよくありました。そのころから一緒に苦労したものですから、小林米作とは何となく戦友というか…

骨を作る骨芽細胞
久米川 現在ではその装置もコンピューター化し、記録もフィルムからテープへと、ある点では効率化しましたね。フィルム時代からの映画制作者も数少なくなった。現在も現役でご活躍の大沼さんは、ドキュメンタリー映画のまさに生き字引ですね。その間、制作された映画は何作品ぐらいになりますか。
大沼 作品数でいうと200ぐらいだと思いますが、かなりのものが賞をいただいています。最近ではピロリを扱ったものが文部大臣賞をいただきました。その前はエイズの問題、それからいろいろな化膿菌の化学療法の問題などを扱っていくつかいい仕事をしています。
久米川 こういう映画を一般の人は、残念ながらほとんど観る機会がないんですね。
大沼 そう多くありません。スポンサーがついている映像が多いですし…
久米川 発注主がいろんな宣伝用として使うことが多いんですね。センターなどで、子どもたちがいつでも観られるような場所があればいいですね。
大沼 そうですね。もう少し一般の人が観られるようにしたいですね。さいたま市にフィルムアーカイブの大きなものができていて、NHKなどが力を入れてやっていますが、そこにはうちの映像はほとんど納めてあって、行けば観られるようにはなっています。しかしまだポピュラーではありませんね。
久米川 生命科学映画で、立派な作品がたくさんあるんですから、もっと教育に生かすべきではないかなと。僕自身1980年ごろから骨の映画をヨネ・プロさんを中心に制作し、特別講義などで使っていましたが、組織とか解剖の講義を、静的なスライドではなくて映画で動的に観てもらうと、学生は理解しやすく、またものすごく感激するんですね。たとえば破骨細胞が癒合して多核になっていく過程などは、ものすごくドラマチックですから。
大沼 そうですね。私どもでこれからホームページを立ち上げて、高校生や大学生に微速度撮影をやってもらおうと企画しているところです。細胞をじっとみつめてみませんかと。1mmの1/100にも満たない細胞が何億と集まって私たちの体をつくっているわけですが、その一つひとつがこんなに真剣に生きているのかと思えば、生命というこんなにきれいな奇跡的な存在をいためるようなことはできなくなると思うんです。中学生や高校生が人を殺してしまうというような騒ぎの中で、生命の見直しをやりましょうと。そういうことも含めて、命を観るということはとても面白いですね。
久米川 研究室で二晩徹夜とか、どこかで合宿が続くとか、生活もどちらかというと不規則でしょう。健康ということではどういうことに気をつけておられますか。

融合する破骨細胞
大沼 特別なことは何もありません。やはりおもしろがってやっているというのが健康の元じゃないですか。好きなことをやれるというのが一番幸せなんでしょうね。それに今はデジタルの時代になっていろんな面で大変楽になりましたしね。
久米川 おいくつになられました? 大沼さんの今後の大きな目標は何ですか。

大沼氏
大沼 80歳になりました。これからはうちで生命科学の映像をやっている人たちがもう少し落ちついて仕事ができるようにしたいということが1つあります。それからこれまでの生命科学のいろいろな映像を、今まではつくりっぱなしになっていたのですが、これをうまく組み立て直して、教育のためというのではなくて、自分たちがミクロの世界についてどういう考えをもったか、それをどういうふうに鑑賞したかというものを、個々の材料ではなくてもっと統合した形で見てもらえるようなものをつくれないかなという希望があります。これは久米川先生の業績についてのフィルムをつくったときに、そういう大きな業績はまとめ方によって非常に面白くなるということが分かりましたので、自分たちの三十何年の業績についても考えて、業績集というのではなくて、細胞をこういう角度で観るとこういうふうに面白いよとか、微速度撮影のために細胞を培養する実験の面白さとか、そういうものをそれぞれの映像作品にしてみんなに見てもらう、そういうこともあるかなと考えています。
久米川 今日はお忙しい中をどうもありがとうございました。
【※微速度撮影】
映画フィルムは被写体の動きを1秒24コマの画像に撮影し、映写も1秒24コマでスクリーンに再現する。もし1時間かかる細胞分裂を1分で見ようとすれば、2.5秒に1コマの微速度撮影をしなくてはならない。ビデオの場合は1秒30コマの画像