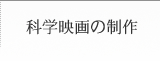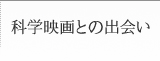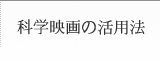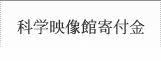- ホーム
- 科学映画の制作
- 科学映画と生物素材

科学映画と生物素材
< 生物資料製作者 浅香時夫 >

生命誕生より
映画の世界に生物素材が登場したのは、理科教材を主題とした教育映画が始まりではないでしょうか。かつては植物の発芽や開花、または発根、色水を使った植物の水上げ実験など、また昆虫の世界では、蝶やトンボの羽化、蝉の羽化など比較的子供の手の届く世界のものが学校教育映画の主役でした。
しかし、現在のような医学や生物科学の生きた素材、特に目に見えない細菌の世界で構成された科学映画は、昭和33年に完成した東京シネマのミクロの世界が、日本では最初ではないでしょうか。結核と戦う体を、菌と細胞とに置き換えて表現した映像は、日本はもとより世界の科学者、医学者に、感動と驚嘆の衝撃を与えたのです。
私がこの世界に入ったのは、ちょうど、この興奮がまだ冷めやらぬ昭和34年前後のころでした。当時、東邦大学の解剖学教室で森於菟教授の、発生学実験の助手をしていたころでした。人を介して、私に東京シネマの岡田桑三社長から、映画の世界にも生物資料製作の研究室を作りたいので参加してほしいとの要請がありました。
そのころの大学は学内紛争のまっ最中で、森於菟教授の鶏胚発生の研究も一段落していたことと、教授の定年とも重なり、教授からも進められたのでこの世界に入りました。
【映画のための素材作り】
こうして私がこの世界で最初の仕事を始めたのは、白金にある東大の伝染病研究所(今の医科学研究所)の病理学教室でした。研究室の一部分を間借りして、ささやかな実験機材を用意して材料作りを始めたのです。
当時東京シネマでは、癌シリーズの3部作を製作中でした。このスタッフは小林米作氏を筆頭に演出、撮影、それに私といつも7~8人で、がん細胞と抗がん剤の戦いを記録していました。
当時研究は、今のように培地も血清も自由に購入できる状態ではなく、すべて自家製です。培養液は処方に従って調整し、血清は芝浦の屠場で牛の血液をもらい、実験室に持ち帰って血清に分離し、濾過滅菌して使用していました。
この培地作りには、3~7日かかりました。この間、撮影スタッフを待たせておけないので、撮影用の材料は、何時も2段階から3段階準備した後、培地作りを始めたのです。
こうして私は、この仕事は大学の研究とはまったく違っていることを強く思い知らされました。培地作りや細胞培養は大学時代と同様ですが、中身が違うのです。
まず、材料(被写体)には、ちりなどの混在は厳禁、正確な現象を発揮する条件を作る。生物被写体の場合は、新しいドラマが起こる材料などが要求される。私が材料作りに参加するまでは、指導学者の研究室に泊まり込んで教室の先生方に材料を作っていただき、それを撮影していたようでした。
従って、もらった材料が良くない場合は、次の材料を作っていただくまで撮影はストップします。それだけ経費はむだになったようです。つまり、営利会社の仕事は、時間と経費が一体で計算されるから、撮影の進行状態で利益が大きく左右されるのです。そこで、私の専門的な材料作りが必要となったのでしょう。学校と会社は根本的に機構が違うということを、身をもって教えられました。
結果的に研究室は、カメラが休むことなく、回転し続けるように材料を供給することが大きな仕事だったのです。この仕事をやってきて、今過去を振り返ってみると、大学時代の研究よりも何倍もの実験と工夫、それに忍耐の繰り返しの連続であったような気がしています。しかしそれによって、誰よりも先に新しい発見も知り神秘的な現象も観察でき、大きな感動と喜びを味合うこともできたことも事実です。
現在の科学は、より複雑に実験、研究が細分化され、生物の世界でも物理や化学、さらには哲学的論理で現象を解明されつつあるのが現状です。お医者さんが、疾患1つを解読するにも数多くの現象を解読し、多くの化学反応を理解して治療薬を選択するのです。
このような論理で埋め尽くされた科学は、どのような映像で表現したら良いのでしょうか。この命題は才能のある若い科学者や芸術家の限りない宿題になっているのかもしれないでしょう。