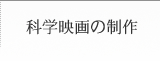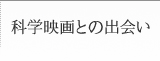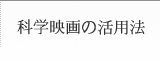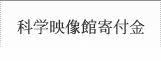荒川のどろつけ
関連ページ
作品概要
制作・企画:荒川流域ネットワーク
2007年 カラー 14分48秒
荒川の氾濫を恵に変えた大宮台地北部地域の巨大客土農法ドロツケは、荒川下流部と特に大宮台地の西縁部(現在の桶川市・北本市)で行われた、荒川の氾濫土を畑に運ぶ客土農法だった。この伝統的な農法について、野外調査研究所理事長の吉川國男氏が詳細に説明している。
ドロツケは、荒川から4㎞以内の黒色腐植土の不足した地域で行われた。農家の男性が冬の仕事として、荒川の氾濫土を袋に入れて馬に乗せ運んだ。数百年に亘り行われた思われるドロツケによる客土の厚さは50㎝から1mに達し、その総量はダンプか−1000万台を超える量となった。ドロツケは、大正時代には廃れはじめたが、昭和30年代まで続けられたという。
氾濫土は燐酸分の補給や酸性の中和などに役立ち、埼玉県の麦作営農地を支えた。荒川の氾濫は危険な自然現象であるが、ドロツケはその土地の人々の命と暮らしを支える重要な役割を果たしていた。(非営利活動法人 荒川流域ネットワーク代表理事 鈴木勝行)
解説
理正大学非常勤講師 吉川國男
補足
「ドロツケとは民族語彙で、荒川下流部とくに大宮台地の西縁部(現在の桶川市・北本市)の人々が、荒川の氾濫土(沖積土)を台地上の畑に運んだ作業を指して言う言葉である。」と埼玉県が編纂した「荒川」の中で、自身も編纂を手掛けた野外調査研究所理事長の吉川國男さんが書かれている。永年の調査研究から、このドロツケ慣行が全国的にも極めて大規模な客土農法だったことが分かってきたということだ。
今はもう途絶えてしまった伝統的な農法について、記録映像に残すため吉川さんを桶川市に訪ねた。吉川さんは私たちの申し出を快く引き受けて、現地を案内しながらドロツケの実態について詳しく説明してくれた。
ドロツケが行なわれた要因は、耕作に不可欠な黒色腐植土の層が薄買ったことにあるという。行なわれたのは、荒川からの距離が4㎞以内の地域であった。ドロツケ作業は農家の男の冬の仕事で、荒川に近い地域では、日に10往復前後、遠い所では3往復前後行なったそうだ。馬にスカリと呼ばれるワラ縄で編んだ袋を左右に載せて高水敷に来て、袋に氾濫土を入れて運んだそうである。毎年運ばれたドロツケの土の厚さは50㎝前後から荒川の河川敷に近い地域では、1mに達する所もあるということだ。このドロツケの土の総量を大雑把に計算したところ、10t積みダンプカーの1,159万2000台分に相当する量になったという。
ドロツケがいつ頃から行なわれるようになったのかは、諸説があり定かではないそうだが、一冬に運べる量は畑全体に広げると約1㎝程であったそうなので、数百年前から行なわれてきたと考えるのが妥当ではないかという。ドロツケは化学肥料の普及、馬に代わる役牛の普及、河川管理上の規制等の理由で、大正時代に止めたところが多かったが、一部の農家は昭和30年代まで継続的に行なっていたという。
埼玉県はかつて、三麦(大麦・小麦・裸麦)の生産量が全国第1位であったが、その中心部がドロツケを行なった荒川左岸沿いの鴻巣市馬室から上尾市平方であったそうだ。この地方の麦は「足立の大麦」といわれ「中山道もの」の銘柄で、市場でも高く取り引きされていたという。この地帯を全国一の麦作営農地として支えていたものは、荒川の氾濫土という恵であったということになる。この土は、霜柱が出来にくく、冬の強風でも飛ばされることがない。また、土壌分析によると、燐酸分の補給や酸性の中和などに役立っていということである。
河川の氾濫は、人の暮らしにとって危険な自然現象だが、同時に周辺の人々の命と暮らしを支える重要な自然現象でもあったことを「ドロツケ」は教えてくれた。(非営利活動法人 荒川流域ネットワーク代表理事 鈴木勝行)